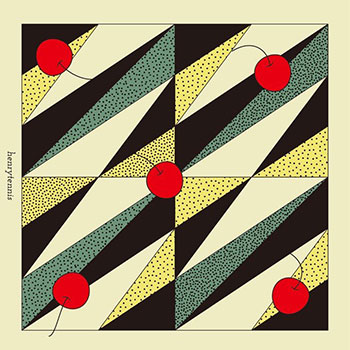henrytennis『Freaking Happy』レビュー
[2019.04.19]
『Freaking Happy』 01. May I Shoot 02. Booked 03. Carbyne 04. Microwaves 05. Harvest 06. Firebird 07. America 08. Silver Christ of Santa Fe OCIRCD-001 2,700円(税込) Natural Hi-Tech Records Inc. 2019.04.17発売
■official web site http://henrytennis.com/ ■twitter https://twitter.com/henrytennis7
すぐれた芸術作品は空虚を含んでいる。制作の過程で厳選され、却下された全ての可能性は、必ず作品から何かを抉り取っていく。鑑賞する者の感動がそこに充填された時、美しさが醸し出されるか否か。それが創作と鑑賞の関係である。 抉られたものがあるということ。文芸で言えば、耳慣れた言葉に、全く新しい響きや情感が宿っているかということ。映画で言えば、フレームに収められなかったものが謎として燃えて、フレームの中にその謎の燃えた香りが流れているかということ。 芸術には謎や不思議があってほしい。なぜこのようなものが生まれたのか、なぜこんなものが崩れずに立ち続けていられるのか? そうした驚きは何物にも代えがたい。 言葉を持たない音楽にも謎がある。というより、生育歴や歌詞から人物的な背景やメッセージが生産されて、ミュージシャンの魅力のありかとして語られることが多い以上、言葉なき音楽は、憶測のフックを持たない表現として謎を見いだされやすい。そもそも、音楽における歌詞とは魅力の謎の解ではなく、「なぜこの歌に惹かれるのか?」という難問であるが。 なぜこうした音色が採り入れられたか? なぜこうした構成が組まれたのか? 聴く者にとっては、これも謎の一種だ。音の強弱、音色の色合いや手ざわり。反復されるフレーズ、その変形の緩やかさや飛躍。そのディテールに目を凝らす時、その音楽がすばらしいものであるなら、自分の物差しでは測り切れない未知を発見できる。 そして音楽の持つ至上の美点は、暴き切れなかった謎を抱えたまま、音に合わせて体を動かして楽しめるということだ。音楽によって踊る時、人の感覚の中には、リニアに加速していく二つの集中が生まれる。音楽を愛好する中で記憶してきた、いくつものパターンのメロディやリズム、それを今聴いているものと照らし合わせる思考。そして、今まさに体に響いてくる音への没入。その二つが相関しながら熱を上げていく時、体温も心地良く上がり、日常からかけ離れた所へ踏み入ったとはっきり分かるほどの多幸感を掴むことが出来る。溶けていくと同時に何かに突き刺さるような、物理法則を無視しているけれどそう存在していることに疑いが挟まらない、ぶっ飛んだ昂揚。 henrytennis の音楽に聴き入り、細部にまで目を走らせることは、とても楽しい。本作『Freaking Happy』の幕開けである『May I Shoot』を聴くだけで、それが分かるだろう。 遅いテンポで管楽器とドラムが鳴り合った後にビートが定まる、交響曲然としたクラシカルな始まり。細やかに音が詰め込まれたドラムにギターが絡みつき、ベースと鍵盤がそれを後ろから押して、勢いが増していく。ギターと鍵盤が一旦退くと、管が徐々に重なり合っていき、一番初めのリフが、今度はビートに寄り添って軽快に奏でられる。管と入れ替わりでギターが戻ってくる、管が別のフレーズでもってそこに加わる。そして続くタメツメの効いた掛け合い。テンションが上がる。しかしそれは、爆発の連続で引き起こされるシンプルな興奮ではない。ロケットの打ち上げのような精緻な加速による、どこかラグジュアリーですらある、滑らかな興奮なのだ。 前に出る/後ろに退く、リードする/協調する、プレイヤーそれぞれの挙動が実に洗練されている。曲の中で新しいフレーズが現れた時、多少なりとも驚きが生ずるものだが、本作ではその驚きのカドが巧みに取られている。劇的な変化が起こっていることはすぐ分かるのに、体は淀みなく次のタームの踊りをおどり始めるのだ。 ユニゾンから誰かが脱していく、もしくは誰かのソロを突き上げるようにユニゾンが再開されて音像が渾沌としていく時にさえ、整然とした美術的な雰囲気が保たれている。どのメンバーも狂騒的なソロを奏ではするが、強固なバッキングの印象が確かであるためか、聴く者の理性は熱狂に覆い尽くされてしまう前に、わずかに掬い上げられる。建物の爆破解体、または映画の中で建造物が崩壊するシーンのような緻密な計算の翳が、随所に垣間見える。 奔放なソロがリレーされていく『Booked』然り、蓄音機から流れているような音質のギターの独奏から、従来の音質のバンドサウンドへとジャンプする『Harvest』然り、目の開くような刺激はいくつも用意されている。そしてそれが、びっくり箱のように短絡的に現出するのではなく、ミステリーのような緻密さによって叙述されている。 そこに気取ったものを感じて鼻白むということが全くなく、むしろ夢中で踊り続けていたくなる、この聴き味の自然さが何とも不思議なのだが、それはその緻密さがマニア的な偏執に収束しているのではなく、《まぶしさ》や《楽しさ》といったエキサイティングな感覚に直結しているためではないか。 1978年に発売された『スペース・インベーダー』ブームを皮切りに、80年代にはアーケードゲームが多く開発された。そして1983年、任天堂が発売したファミリーコンピュータは家庭用ゲーム機の普及の起爆剤となり、多くのアーケードゲームを移植発売するに至った。 ゲーム音楽ファンの間でよく取り沙汰されるのが、アーケードからファミコンに移植されたゲームのBGMのチープさである。ファミコンの処理装置では、基本的に四つの音しか同時に再生させることが出来ない(しかも四音のうちの一音は音階を持たないホワイトノイズで、それによってドラムやパーカッションの音を表現していた)。また、それを再生する音響機器というのは、当然ながらテレビのスピーカーだ。拡張音源を搭載したゲームソフトも例外的に存在するが、音源ICとサウンドシステムが一つの筐体としてデザインされたアーケードゲームとは、音のリッチさの面では比べるべくもない。ファミコンで慣れ親しんだ作品のアーケード版に触れると、音響面において、新鮮さだけで体が後ろに傾ぐような感動を覚える。 henrytennis の音のまばゆさや楽しさは、そうしたリッチな圧倒にどこか似ている。 初めに言及した『May I Shoot』は、ハーモニーの豊かさやドラムのトリッキーな音の詰め方だけにピントを合わせても楽しめるが、あえて頑なに一定のテンポで体を揺らし続けていると、うねるギターに挑発されているような、ソプラノサックスのロングトーンと一緒へ遠くまで飛ぶような感覚を味わえて面白い。『America』はドラムとキーボードの抑制の効いた演奏から始まるが、そこにベースが加わり、ギターが加わり、サックスが加わりとしていくうちに、それぞれの演奏が徐々に熱を持って変形していく、その過程にドラマを感じる佳曲だ。その変形を追いかけてゆく時、植物の成長を早回しの映像で見るように、少し背徳的な贅沢を感じられる。『Firebird』の緩急の効かせ方、例えばタイトなパートの間でトロンボーンの音が柔らかに立ちあがってくるくだりなど、それこそ暗がりから歩み出た瞬間に似て、まぶしい。 どこを見ても精巧でありながら、全部の音をただ聴いて体を揺らしたり足を踏み鳴らしたりする、そういう洗練からかけ離れた素直な振る舞いでも揺らがないほど、まず演奏そのものが楽しいのだ。 このアルバムの複雑さは、鑑賞を重ねるほどに味わいを増していく。それでも、まずはこのアルバムの楽しさに、楽しんでいる自分を正面からぶつけてみてほしい。楽しさの波が相殺された後で、より静かに、よりつぶさに、このアルバムの不思議を見つめることができる。 (文:オオクマシュウ)